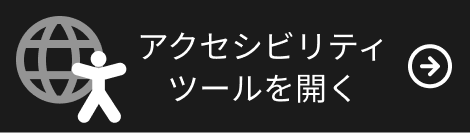疾患の概要
細菌性腟症(BV)は、腟の中の常在菌バランスが崩れることで起こる代表的な腟のトラブルです。性感染症(STI)とは少し違い、性行為の有無に関係なく起こることがありますが、複数のパートナーがいる場合や避妊具を使用しない性行為が関係することもあります。BVは放置すると他の性感染症にかかりやすくなったり、妊娠中には早産などのリスクにつながることもあり、きちんとした診断と治療が大切です。
主な症状
BVの典型的な症状は次のとおりです。
- 帯下増加、下腹部痛、不正出血が3大症状
- 外陰部のかゆみや強い炎症はあまり見られない
症状がはっきり出ない人も多く、自覚のないまま検査でわかるケースもあります。
原因とメカニズム
健康な腟内は「乳酸菌(ラクトバチルス)」が多く、弱酸性(pH 3.8〜4.5)に保たれています。BVでは、この乳酸菌が減り、大腸菌や嫌気性菌(Gardnerella vaginalisなど)が増えてしまうことで、腟内がアルカリ性に傾きます。その結果、おりものやにおいの変化が起こります。
診断
診察や検査では以下の基準が用いられます。
【アムセル基準(臨床診断基準)】以下の4つのうち3つ以上でBVと診断します。
- 均一で薄い白色の膣分泌物
- 腟内pHが4.5以上
- おりものに10%KOH液を加えると魚臭が出る(Whiffテスト陽性)
- 顕微鏡で「Clue cell」と呼ばれる特徴的な細胞が見られる
【点数化診断(Nugentスコアなど)】顕微鏡で腟内細菌の種類やバランスを評価する方法。
治療方法
BVは自然に治ることもありますが、再発しやすいのが特徴です。妊娠中や症状が強い場合は治療を行います。
- 抗菌薬の内服や膣剤(メトロニダゾール)
※妊娠中の方は赤ちゃんへの影響を考慮して薬の種類や使い方が調整されます。必ず医師の指示に従ってください。
妊娠への影響
妊婦さんがBVを放置すると、早産、前期破水、絨毛膜羊膜炎などのリスクが高まることが報告されています。そのため妊婦健診などでBVが見つかった場合には、必要に応じて治療を行います。
再発と予防
BVは治療後も再発しやすい感染症です。予防のためにできることは以下です。
- 腟洗浄を頻繁にしすぎない(自浄作用が乱れる原因になります)
- 避妊具(コンドーム)を使う
- 喫煙を控える(喫煙は再発のリスクになります)
- パートナーも含めた生活習慣の見直し
最後に
細菌性腟症は「おりもののにおいが気になる」という比較的よくある症状の背景にあるものです。性感染症とは異なりますが、放置してよいわけではなく、とくに妊娠中は母体と赤ちゃんに影響することもあります。気になる症状がある方は、恥ずかしがらずに早めに婦人科で相談してください。